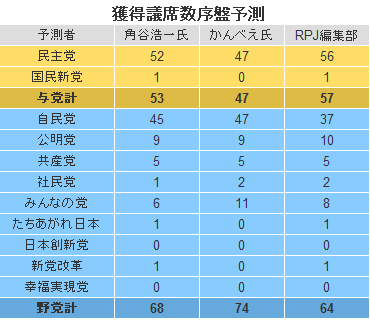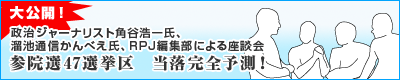
出席者
政治ジャーナリスト: 角谷浩一氏 文中では【角谷】
溜池通信主催: かんべえ氏 文中では【かんべえ】
RPJ編集部: 編集部Y 文中では【RPJ編集部】
溜池通信主催: かんべえ氏 文中では【かんべえ】
RPJ編集部: 編集部Y 文中では【RPJ編集部】
第1回 2010参院選予測座談会PART1 [ 2010参院選の見方 ]
鳩山内閣で一時期20%にまで下がった内閣支持率は、菅直人新内閣の発足を契機に、民主党支持率とともに復調した。民主党幹部ですら驚きの回復を見せた内閣支持率ではあるが、このまま参院選を乗り切れるとは誰も思っていないだろう。昨年の政権交代の屈辱から再起を期す自民党、政界再編に向けた第三極の風を吹かせようとするみんなの党など、政治情勢は流動的だ。
消費税増税という大きなテーマもあり、日本の将来を占うとも言える今回の参院選の行方を、政治・選挙に精通した2人の評論家、政治ジャーナリストの角谷浩一氏と「溜池通信」を主催するかんべえ氏を招き、RPJ編集部を交え、「参院選予測座談会」と題してお話を伺った。
消費税増税という大きなテーマもあり、日本の将来を占うとも言える今回の参院選の行方を、政治・選挙に精通した2人の評論家、政治ジャーナリストの角谷浩一氏と「溜池通信」を主催するかんべえ氏を招き、RPJ編集部を交え、「参院選予測座談会」と題してお話を伺った。
【RPJ編集部】
まず参院選について全般的なお話を。
【かんべえ】
いまの状況は1998年の参院選の状況によく似てきたと思います。二大政党支持以外の無党派がすごく増えていたこと、また、選挙直前になって消費税など税金の話が出てきたことなど、雰囲気が似てきています。
あのときは橋本龍太郎元首相、いまは菅首相。ひょっとすると直前の首相の一言でがらりと情勢が変わることがあるのかなあと。
なので、今の時点での支持率は真に受けないほうがいいと思っています。
あのときは橋本龍太郎元首相、いまは菅首相。ひょっとすると直前の首相の一言でがらりと情勢が変わることがあるのかなあと。
なので、今の時点での支持率は真に受けないほうがいいと思っています。
【角谷】
菅内閣の高支持率での発足というのは、ここ数年間の新内閣も高い支持率で発足し、そのあとどんどん支持率が下がっていくのを見ると、もはや慣例だ。これは前の政権よりも、ましになるだろうという期待が有権者の中に強くあって、発足時の支持率が非常に高く出る。支持するのは仕事をしていないから支持できるということで、実際に仕事をし始めると下がってしまうというのは、自民党政権末期から民主党政権にかけても傾向は同じだ。
つまり、国民は政治に絶えず期待はしているけれども、ふたを開けてみるとがっかりする、というのが顕著な傾向だ。鳩山内閣も、菅内閣も同様に、それは麻生太郎内閣、福田康夫内閣、安倍晋三内閣でも同じだったと言える。
つまり、国民は政治に絶えず期待はしているけれども、ふたを開けてみるとがっかりする、というのが顕著な傾向だ。鳩山内閣も、菅内閣も同様に、それは麻生太郎内閣、福田康夫内閣、安倍晋三内閣でも同じだったと言える。
菅首相の人物評
【角谷】
菅さんの政治的スタンスがかなりわかってきた。新しいことはやらない。今まで自民党がやってきたスタンスでもいいと。やるのが俺ならばいいという傾向。党が持っている政策ではなく、「俺が運営する」というところに力点があるという感じがした。
かんべえさんのご指摘のように、選挙の直前であることを考えると、国会を何も言わずに閉じて、そのあと消費税議論を仕掛けるというのは、石破茂自民党政調会長の言うように、「抱きつきおばけ」だなと。
かんべえさんのご指摘のように、選挙の直前であることを考えると、国会を何も言わずに閉じて、そのあと消費税議論を仕掛けるというのは、石破茂自民党政調会長の言うように、「抱きつきおばけ」だなと。
【かんべえ】
菅さんという人はどんな人かということですが、政策は「空き缶」、政局は「バルカン」。小政党から出てきて成り上がるというような。
いまはその「空き缶」に、財務省のひとが政策をうまく入れたなあという印象です。消費税の話も、G20の直前にやるというのはとてもいいことで、カナダのG20は「財政どうしましょうサミット」ですから、日本は自分で借金を返す気があるというのを見せないといけない。
そのことを考えると正しいのでしょうが、ただ、消費税の話をして、選挙によかったことはないというのも過去の経験則です。なので、向こう一か月の間にいろいろあるでしょうね。
いまはその「空き缶」に、財務省のひとが政策をうまく入れたなあという印象です。消費税の話も、G20の直前にやるというのはとてもいいことで、カナダのG20は「財政どうしましょうサミット」ですから、日本は自分で借金を返す気があるというのを見せないといけない。
そのことを考えると正しいのでしょうが、ただ、消費税の話をして、選挙によかったことはないというのも過去の経験則です。なので、向こう一か月の間にいろいろあるでしょうね。
【RPJ編集部】
菅総理は「お坊ちゃん政治家とは違うな」というのがこの2週間の感想です。
それは今回の消費税論議の持ち出し方、つまり自民党が10%に言及したことに対して持ち出したこと。石破さんの言う「抱きつきおばけ」ですけど、そういう手法は上手です。
他にも、菅さんの言っている「強い経済、強い財政、強い社会保障」というのはたちあがれ日本が党の方針としてしばらく前に打ち出したものをそのまま使ってしまっていて、そういうこともできる。
選挙戦の仕掛けというのも菅さんの動物的な勘で高支持率のまま突っ込もうとしている。比較したいのは、麻生内閣が高支持率のなかですぐに選挙を打つべきかどうかという時に、麻生さんは衆議院を解散できず、周りにいた側近が解散を阻止して、自民との歴史的大敗につながったわけですが、菅氏はその教訓を見ていて、その轍を踏まないために、批判があっても国会を閉めて、選挙に突っ込んだ。
ネット選挙解禁が実現できなかったので、残念ながら今回の選挙もアジェンダセッターは既成メディアになるのでしょうが、前回の衆議院の前はメディアにも政権交代を是だとするという雰囲気がありました。消費税の取り上げ方も含めて、メディアには「民主党を敗北に追い込んで政治を面白くしてやろう」という覚悟はできてないのではないか。
ということは、この一か月の間で失言や失政があったとしても、選挙結果や支持率がいきなり急変しないのではないかと見ています。
有権者の側にも昨年の衆院選のときには政権交代の実現という熱気があったのが、冷めてしまって、民主党への失望感もあって、投票率が下がる可能性がある。特に若い世代では、ネット解禁の法律が整備されなかったことも影響があって、「政治は結局無力なんだ」という雰囲気が蔓延するとすれば、50%代前半になるのでは。
他にも、菅さんの言っている「強い経済、強い財政、強い社会保障」というのはたちあがれ日本が党の方針としてしばらく前に打ち出したものをそのまま使ってしまっていて、そういうこともできる。
選挙戦の仕掛けというのも菅さんの動物的な勘で高支持率のまま突っ込もうとしている。比較したいのは、麻生内閣が高支持率のなかですぐに選挙を打つべきかどうかという時に、麻生さんは衆議院を解散できず、周りにいた側近が解散を阻止して、自民との歴史的大敗につながったわけですが、菅氏はその教訓を見ていて、その轍を踏まないために、批判があっても国会を閉めて、選挙に突っ込んだ。
ネット選挙解禁が実現できなかったので、残念ながら今回の選挙もアジェンダセッターは既成メディアになるのでしょうが、前回の衆議院の前はメディアにも政権交代を是だとするという雰囲気がありました。消費税の取り上げ方も含めて、メディアには「民主党を敗北に追い込んで政治を面白くしてやろう」という覚悟はできてないのではないか。
ということは、この一か月の間で失言や失政があったとしても、選挙結果や支持率がいきなり急変しないのではないかと見ています。
有権者の側にも昨年の衆院選のときには政権交代の実現という熱気があったのが、冷めてしまって、民主党への失望感もあって、投票率が下がる可能性がある。特に若い世代では、ネット解禁の法律が整備されなかったことも影響があって、「政治は結局無力なんだ」という雰囲気が蔓延するとすれば、50%代前半になるのでは。
【かんべえ】
参院選の投票率の過去のパターンで言うと、だいたい50%台。ざっくり有権者数が1億人いるうちで、5,500~5,900万人程度で過去の参院選は収斂している。
私はそうはいっても、無党派層は去年の選挙で味をしめたと思っています。自分たちが投票すると、政治家があたふたする、状況が変わるということを学習したと思っています。
なので、3年前もそうですけど与党へお灸を据えると。今回の民主党へも積極的にお灸をすえるのではないかと見ています。
私はそうはいっても、無党派層は去年の選挙で味をしめたと思っています。自分たちが投票すると、政治家があたふたする、状況が変わるということを学習したと思っています。
なので、3年前もそうですけど与党へお灸を据えると。今回の民主党へも積極的にお灸をすえるのではないかと見ています。
角谷氏「今回の参院選でマニフェスト選挙が終わる」
【角谷】
今回の選挙のひとつの大きなポイントは、「マニフェスト選挙がこれで終わる」ということだと思う。
マニフェストというのは政権公約と言いながら、今回の参院選での新マニフェストの中身は事実上、ほとんど交代し、目玉政策も工程表もなくし、スローガンに落とし込んでしまったということを考えると、政権交代の大きな旗印としたマニフェストを、野党第一党のときには使えるが、政権をとったあとには有効でないということを1年も持たずに民主党自身が認めざるを得ないのではないか。
また、保守系新党が乱立することで、マニフェストも乱立した。マニフェストは、2大政党のどちらがいいのかという判断基準になるということがあるが、たくさん出ると、ここの政党のこの政策はいい、ここはやだということになる。
こうなってくると、マニフェスト自体が混乱の根本になる可能性が出てくる。それが選挙を混乱させる。めんどくさい、わからない。これが投票行動にどう出るかというと、選挙に行くのをやめるという判断になるのではないかと思う。
まだ1か月あるので総理の発言に対して左右されることは当然ある。ただ、総理の発言に有権者が敏感に反応するかというと、メディアが反応したことを受けて、「おかしいのかもしれない」という反応をするのではないか。こういったことを選挙前に言うべきか、終わった後に言うべきかを解説するのはメディアであって、そういう意味では大きくバイアスがかかる可能性がある。そういう意味では、マニフェストでないところで騒動を起こそうとする総理の発言というのは、自らマニフェストを否定したと言ってもいいのではないか。
マニフェストというのは政権公約と言いながら、今回の参院選での新マニフェストの中身は事実上、ほとんど交代し、目玉政策も工程表もなくし、スローガンに落とし込んでしまったということを考えると、政権交代の大きな旗印としたマニフェストを、野党第一党のときには使えるが、政権をとったあとには有効でないということを1年も持たずに民主党自身が認めざるを得ないのではないか。
また、保守系新党が乱立することで、マニフェストも乱立した。マニフェストは、2大政党のどちらがいいのかという判断基準になるということがあるが、たくさん出ると、ここの政党のこの政策はいい、ここはやだということになる。
こうなってくると、マニフェスト自体が混乱の根本になる可能性が出てくる。それが選挙を混乱させる。めんどくさい、わからない。これが投票行動にどう出るかというと、選挙に行くのをやめるという判断になるのではないかと思う。
まだ1か月あるので総理の発言に対して左右されることは当然ある。ただ、総理の発言に有権者が敏感に反応するかというと、メディアが反応したことを受けて、「おかしいのかもしれない」という反応をするのではないか。こういったことを選挙前に言うべきか、終わった後に言うべきかを解説するのはメディアであって、そういう意味では大きくバイアスがかかる可能性がある。そういう意味では、マニフェストでないところで騒動を起こそうとする総理の発言というのは、自らマニフェストを否定したと言ってもいいのではないか。
【かんべえ】
マニフェストについては、違う意味から同感です。むしろ早く間違いに気付いてくれてよかったと思っています。
というのも、マニフェストというのは「党の理念」を示すもので、「何年までにいくら配ります」というのは、本来は政策としてうたう必要がないのではないかと思います。
そういうのはいくらでも状況は変化していくわけで、現にユーロ危機だとかが起きているわけですね。そうじゃなくて、「我が党の理念はこうです」というのがイギリスのマニフェストであり、アメリカのプラットフォームなのです。日本も早く間違いに気付いて、恥ずかしいからみんななかったことにしたほうがいいのではないかと思います。
というのも、マニフェストというのは「党の理念」を示すもので、「何年までにいくら配ります」というのは、本来は政策としてうたう必要がないのではないかと思います。
そういうのはいくらでも状況は変化していくわけで、現にユーロ危機だとかが起きているわけですね。そうじゃなくて、「我が党の理念はこうです」というのがイギリスのマニフェストであり、アメリカのプラットフォームなのです。日本も早く間違いに気付いて、恥ずかしいからみんななかったことにしたほうがいいのではないかと思います。
有権者の民意より優先される少数意見
【角谷】
そもそもマニフェストが有効に機能するのは、知事選や市長選のような場所。「4年間で私の政策はこれをやり遂げたい。それが決着しない場合はもう4年ください」という理屈ならわかる。実際に、4年間の自分の政権を維持できる担保があるのは、知事や市長くらい。
もうひとつマニフェストのいかがわしい部分だと思うのは、連立与党になったら違うマニフェストが選挙後に出てくるところ。これはおかしい。
もうひとつマニフェストのいかがわしい部分だと思うのは、連立与党になったら違うマニフェストが選挙後に出てくるところ。これはおかしい。
【かんべえ】
そうですね。それも300議席の党じゃなくて5議席くらいの党のマニフェストがね。
【角谷】
少数党のマニフェストが気に入らないというと、連立でどちらかというとおんぶされている方が怒り出す。
こういう理屈はおかしい。有権者の民意はどこに反映されるのか。
こういう理屈はおかしい。有権者の民意はどこに反映されるのか。
【かんべえ】
300議席の政党に民意があるのは当たり前なんです。
【角谷】
その通り。有権者の民意を無視した三党連立の方が優先されるのであれば、選挙の意味はあるのか。連立与党のマニフェストを最初から出せばいいのではないかと思う。
【かんべえ】
二大政党制についてもうひとつ。イギリスで「オポジッション(野党)」というのは第二勢力の野党のことしか言わないです。英国議会でも「スコットランド国民党」などの小党はありますが、小さな政党は「野党」とは言わないわけです。
【角谷】
少数政党、諸派はどう扱うのかということだが。例えば、東京都知事選の候補者ディベートを行うといったときにどこまで候補者を呼ぶのか、というのが問題になる。立候補者は「全部呼ぶべきだ」という理屈もわかるが、主要政党の候補が来なかったら困るので、「主要候補者」とか理屈を付けて5、6人に絞り込む。
問題は、「なぜうちの党を呼ばないのか」という声だが、では、議会のなかで議員数10人に満たないような政党の声を拾う必然性はどうやって担保するのかということ。連立マニフェスト、3党合意ということを議論していくと、政党とはどういう枠組みを理解すると、国民の声を代弁する有効政党であると考えるべきなのかというのはものすごく難しい。
今回も新党がたくさん立ち上がったが、なにをやる党なのか、議席が少ないからあまり扱うべきではないということになるとこれまたおかしな問題が起こるということを言うが、メディアはよく街の声を聞くというのをやる。実際やると、8割ぐらいが○で2割が×というときに、放送のときには同じくらい出て、同じくらいの街の声があると思ってしまうというのがある。これは「公正を装うマジック」。こういったことをどう考えるか。国民も「これはどうなんですか」と言っていいのでは。
問題は、「なぜうちの党を呼ばないのか」という声だが、では、議会のなかで議員数10人に満たないような政党の声を拾う必然性はどうやって担保するのかということ。連立マニフェスト、3党合意ということを議論していくと、政党とはどういう枠組みを理解すると、国民の声を代弁する有効政党であると考えるべきなのかというのはものすごく難しい。
今回も新党がたくさん立ち上がったが、なにをやる党なのか、議席が少ないからあまり扱うべきではないということになるとこれまたおかしな問題が起こるということを言うが、メディアはよく街の声を聞くというのをやる。実際やると、8割ぐらいが○で2割が×というときに、放送のときには同じくらい出て、同じくらいの街の声があると思ってしまうというのがある。これは「公正を装うマジック」。こういったことをどう考えるか。国民も「これはどうなんですか」と言っていいのでは。