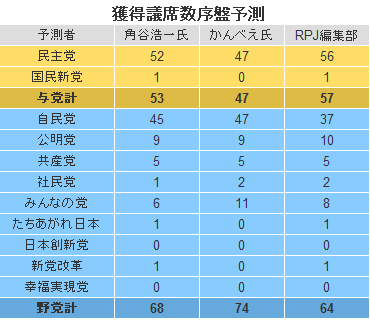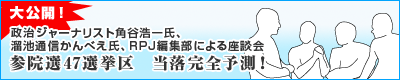
出席者
政治ジャーナリスト: 角谷浩一氏 文中では【角谷】
溜池通信主催: かんべえ氏 文中では【かんべえ】
RPJ編集部: 編集部Y 文中では【RPJ編集部】
溜池通信主催: かんべえ氏 文中では【かんべえ】
RPJ編集部: 編集部Y 文中では【RPJ編集部】
第1回 2010参院選予測座談会PART1 [ 2010参院選の見方 ]
鳩山内閣で一時期20%にまで下がった内閣支持率は、菅直人新内閣の発足を契機に、民主党支持率とともに復調した。民主党幹部ですら驚きの回復を見せた内閣支持率ではあるが、このまま参院選を乗り切れるとは誰も思っていないだろう。昨年の政権交代の屈辱から再起を期す自民党、政界再編に向けた第三極の風を吹かせようとするみんなの党など、政治情勢は流動的だ。
消費税増税という大きなテーマもあり、日本の将来を占うとも言える今回の参院選の行方を、政治・選挙に精通した2人の評論家、政治ジャーナリストの角谷浩一氏と「溜池通信」を主催するかんべえ氏を招き、RPJ編集部を交え、「参院選予測座談会」と題してお話を伺った。
消費税増税という大きなテーマもあり、日本の将来を占うとも言える今回の参院選の行方を、政治・選挙に精通した2人の評論家、政治ジャーナリストの角谷浩一氏と「溜池通信」を主催するかんべえ氏を招き、RPJ編集部を交え、「参院選予測座談会」と題してお話を伺った。
かんべえ氏「マニフェストはそれを語る政治家の力量を見抜くもの」
【RPJ編集部】
これはカンベエさんの持論ですが、選挙結果によっては「民みん公(民主党、みんなの党、公明党)」の3党連立が新たに生まれる可能性がある。国民新も消費税や今回の選挙によって対応が変わるかもしれない。
そういう意味では、もう少し大きな党同士での連立というのが、選挙後に起きるかもしれない。
昨年の衆院選と今回の参院選でマニフェストの中身が違っても民主党が負けなかったら、お二人が言うように、マニフェスト選挙の意味がなくなるのだろうとおもいます。
また、「オポジッション」であるべき自民党の政策やマニフェスト作りを仄聞(そくぶん)したところによると、消費税増税10%明記の書きぶりも含めて、未だに「与党ぼけ」しているらしい。野党としての政権与党の攻め方についての展望がないままの議論が行われて、今回のマニフェストもこなれていて過激さがない。やはり50数年間政権交代が無かった影響は大きくて、与党も野党も自分たちの立ち位置が決められないままで選挙戦に突入してしまった感じがして、嘆かわしいですね。これも民主主義のコストですが。
そういう意味では、もう少し大きな党同士での連立というのが、選挙後に起きるかもしれない。
昨年の衆院選と今回の参院選でマニフェストの中身が違っても民主党が負けなかったら、お二人が言うように、マニフェスト選挙の意味がなくなるのだろうとおもいます。
また、「オポジッション」であるべき自民党の政策やマニフェスト作りを仄聞(そくぶん)したところによると、消費税増税10%明記の書きぶりも含めて、未だに「与党ぼけ」しているらしい。野党としての政権与党の攻め方についての展望がないままの議論が行われて、今回のマニフェストもこなれていて過激さがない。やはり50数年間政権交代が無かった影響は大きくて、与党も野党も自分たちの立ち位置が決められないままで選挙戦に突入してしまった感じがして、嘆かわしいですね。これも民主主義のコストですが。
【かんべえ】
私は、マニフェストというのはビジネスモデルのようなものだと思います。ビジネスモデルをもってくる起業家がいる。そして有権者はベンチャーキャピタルですから、誰にお金を投資すべきかということを判断する。
それぞれに自分のビジネスモデルはこうですと語る。で、投資家はそのビジネスモデルに投資するのかというと違いますよね。
結局はビジネスモデルというのは絵空事ですので、ビジネスモデルを語る起業家の力量を見抜くわけです。マニフェストを語る政治家を、国民としてはそれを見抜かなければいけないということです。
このビジネスモデルというものは、現実には、会社を興した翌日には無駄というか、役に立たなくなるものです。あらためて「紙切れより人が大事」なんだということころじゃないでしょうか。
それぞれに自分のビジネスモデルはこうですと語る。で、投資家はそのビジネスモデルに投資するのかというと違いますよね。
結局はビジネスモデルというのは絵空事ですので、ビジネスモデルを語る起業家の力量を見抜くわけです。マニフェストを語る政治家を、国民としてはそれを見抜かなければいけないということです。
このビジネスモデルというものは、現実には、会社を興した翌日には無駄というか、役に立たなくなるものです。あらためて「紙切れより人が大事」なんだということころじゃないでしょうか。
【角谷】
なぜこうなったかというと、2003年の小泉・菅対決なんですよ。そのときの党首討論、民主党は当時の菅代表が「マニフェスト選挙、やったらいいじゃないか」と詰め寄ったとき、自民党の小泉首相は反論できなかった。
その後、全党合意のうえ、公職選挙法の改正でマニフェスト選挙ができるようになった。あのころのことを思い出して頂くと、小泉さんのワンワードポリティックスである「郵政民営化」に対して、民主党は太刀打ちできなかった。うちは中身の各論がちゃんとありますよ、というのを見せて対抗するしかなかった。
カンベエさんの言うような、「実行する顔が誰か」というのが正しいのにも関わらず、顔がない分、政策で勝っていますという分厚い紙を作らないと小泉さんパワーに対抗できなかったというのが民主党の現実的な弱点だったと言える。
これが野党第一党として、政権交代にこぎつけちゃったら、マニフェストを捨てるわけにいかないんだけど、結果的には、ここで政権とって1年たたないうちにマニフェストが疑わしいものだと有権者も気付いたというか、民主党自身も白状せざるを得なかったということが言えると思う。
その後、全党合意のうえ、公職選挙法の改正でマニフェスト選挙ができるようになった。あのころのことを思い出して頂くと、小泉さんのワンワードポリティックスである「郵政民営化」に対して、民主党は太刀打ちできなかった。うちは中身の各論がちゃんとありますよ、というのを見せて対抗するしかなかった。
カンベエさんの言うような、「実行する顔が誰か」というのが正しいのにも関わらず、顔がない分、政策で勝っていますという分厚い紙を作らないと小泉さんパワーに対抗できなかったというのが民主党の現実的な弱点だったと言える。
これが野党第一党として、政権交代にこぎつけちゃったら、マニフェストを捨てるわけにいかないんだけど、結果的には、ここで政権とって1年たたないうちにマニフェストが疑わしいものだと有権者も気付いたというか、民主党自身も白状せざるを得なかったということが言えると思う。
【かんべえ】
やっぱり0と1との違いというのは大きいんですね。今まで政権に就いたことがなかった人たちが言っている約束は、それだけのものだったと言えるでしょうね。
【角谷】
机上の論理で考えるのと現実は全然違う。そこで修正するなり、諦めるなり、謝るなりというときに、今度はこの人があやまるなら、清々しさを感じるか、嘘臭さを感じるか。今後、こういった始末をつけることを、菅氏ができるのか、できないのか。むにゃむにゃした言い方でやったら、国民はだまされたということになる。
でも、それは野党第一党の限界だし、現実だろう。「いいと思ってやったけど世の中、甘くありませんでした」ということを誰が謝るか、言うのかだが、むにゃむにゃっとやってしまったら、民主党に対する根本的な期待が有権者から崩れていくということだと思う。
でも、それは野党第一党の限界だし、現実だろう。「いいと思ってやったけど世の中、甘くありませんでした」ということを誰が謝るか、言うのかだが、むにゃむにゃっとやってしまったら、民主党に対する根本的な期待が有権者から崩れていくということだと思う。
2003年のマニフェストにもあった「最小不幸社会」
【かんべえ】
2003年の菅さん民主党が掲げたマニフェストには、「つよい日本をつくる」が入っていたし、「最小不幸社会」という言葉も入っていました。
このように使い古しのアイデアを持ってきていたりするわけですよね。まあ、それは当たり前で、画期的な政策や魔法のような政策はないので、そこはいろんなものを使って有り合わせのものでやっていくしかない。
あと、英国政治における「オポジッション」という言葉は、正確には「前の選挙までは政権にいた政党」ということらしいんですね。
なので、自民党が日本における初めての「オポジッション」なんですね。だから、まだ民主党は「オポジッション」になったこともない。政権交代やってみてとてもよかったということも言える。
マニフェストであっても出来ないことは出来ないということを、学習できたというのは非常にいいことだと思う。なので、角谷さんの言うとおり、今後はどうお詫びするのかが鍵じゃないでしょうか。
このように使い古しのアイデアを持ってきていたりするわけですよね。まあ、それは当たり前で、画期的な政策や魔法のような政策はないので、そこはいろんなものを使って有り合わせのものでやっていくしかない。
あと、英国政治における「オポジッション」という言葉は、正確には「前の選挙までは政権にいた政党」ということらしいんですね。
なので、自民党が日本における初めての「オポジッション」なんですね。だから、まだ民主党は「オポジッション」になったこともない。政権交代やってみてとてもよかったということも言える。
マニフェストであっても出来ないことは出来ないということを、学習できたというのは非常にいいことだと思う。なので、角谷さんの言うとおり、今後はどうお詫びするのかが鍵じゃないでしょうか。
【角谷】
「国民と政権の約束だ」とあれだけ言ったのに、約束の不履行をむにゃむにゃとしちゃうのは、ビジネスモデルとして破綻だよね。政策も中身も大事だけど、それを誰が実行するか、それを誰が「できません」と謝るか。その「顔」がとても大事だ。
【かんべえ】
ビジネスでは、利益がどれだけ上がったかというかたちで投資家に報いることができるからいいんだけど…。
マニフェストとビジネスモデルの違いは、明確な評定方式がない世界でどうやって過去のコミットメントを修復していくかということでしょう。
マニフェストとビジネスモデルの違いは、明確な評定方式がない世界でどうやって過去のコミットメントを修復していくかということでしょう。
角谷氏「けっきょくは自民党と変わらないなあ」
【RPJ編集部】
マニフェストに向いているのは首長の選挙で、自分のマニフェストがどれだけ進んだかということを4年ごと自分の政策の進捗度や内部・外部の評価を世の中に示して、それに対して「信を問う」ということがあるべき姿ですよね。
【角谷】
1年間の通信簿であるならいいけど、民主党はマニフェストを変えた。政権を取ったときの「4年間で実現します」という約束を1年目で変えたら、通信簿ができないじゃないか。
【RPJ編集部】
メディアとしてできるのは、公約にかかげたことの進捗度はどうかということを少なくとも有権者に思い出させること。たった10カ月でも最近の鳩山・小沢両氏が辞めたということは覚えているが、普天間のことも、それ以前の郵政の社長人事や、仕分けの失敗については、忘れている。
メディアは少し与党に批判的に有権者に思い出させて、そのことについて「信を問う」といったことが今回の選挙でのメディアの責任だと思うが、実際には難しいでしょう。
メディアは少し与党に批判的に有権者に思い出させて、そのことについて「信を問う」といったことが今回の選挙でのメディアの責任だと思うが、実際には難しいでしょう。
【角谷】
その検証はとても重要なこと。だが、いまの話でなにが見えたかというと、「けっきょくは自民党と変わらないなあ」ということ。
民主党が「自民党の悪行」と言ってきて政権交代をしたが、実際やってみると、「最大公約数的な判断はこうならざるを得ない。そういうものだったんだ」ということを民主党が気付いたとしたら、それは学習ではないか。ただ、それを外から見て学習とみるか失敗とみるかは有権者の判断ではある。それについてはこちら側で限定する必要はないと思う。
ただ、それを凌駕するものが自民から出てきてないということも問題だと思う。もっと気のきいた反撃があったのではないか。なぜいまの自民党が有権者から評価されてないのか、去年の暮れにやった選挙後の分析がまだ甘いということなんだろう。
ところが、それをもう乗り越えたという気持ち、つまり「与党ぼけ」が治らない。もっと言うと、「野党ぶりっこ」みたいなのが上手にできていない。野党になりきれてないから、野党の勉強をするべき。でも、お互いに知恵を出す能力は政党間にはない。
「抱きつきおんぶおばけ」はもしかしたらSOSなのか、それともけっきょく混ぜ返してしまって批判をかわすだけなのか、それも見極めなければならない。
枝野幹事長は「野党第一党に相談するのは当然だ」と言ったが、これを当然とする理屈は、過去の戦後政治にはあまりなかった気がするが。
民主党が「自民党の悪行」と言ってきて政権交代をしたが、実際やってみると、「最大公約数的な判断はこうならざるを得ない。そういうものだったんだ」ということを民主党が気付いたとしたら、それは学習ではないか。ただ、それを外から見て学習とみるか失敗とみるかは有権者の判断ではある。それについてはこちら側で限定する必要はないと思う。
ただ、それを凌駕するものが自民から出てきてないということも問題だと思う。もっと気のきいた反撃があったのではないか。なぜいまの自民党が有権者から評価されてないのか、去年の暮れにやった選挙後の分析がまだ甘いということなんだろう。
ところが、それをもう乗り越えたという気持ち、つまり「与党ぼけ」が治らない。もっと言うと、「野党ぶりっこ」みたいなのが上手にできていない。野党になりきれてないから、野党の勉強をするべき。でも、お互いに知恵を出す能力は政党間にはない。
「抱きつきおんぶおばけ」はもしかしたらSOSなのか、それともけっきょく混ぜ返してしまって批判をかわすだけなのか、それも見極めなければならない。
枝野幹事長は「野党第一党に相談するのは当然だ」と言ったが、これを当然とする理屈は、過去の戦後政治にはあまりなかった気がするが。
【かんべえ】
年金改革の時に三党でやろうと持ちかけたことはあったよね。結局何もしなかったけれど。
【角谷】
そう。だが、その「当然」というのは、ねじれがあるとか、状況がうまくいかない時はともかく、この場合「みんなで渡ろう」というSOSに近いと感じたんだが、どうだろうか。